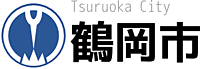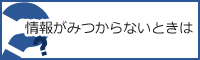国民健康保険税について
更新日:2025年6月26日
国民健康保険税のあらまし
国民健康保険税(国保税)は、会社や官庁などの健康保険に加入していない方を対象に医療の給付等を行うことを目的とした国民健康保険(国保)事業の費用に充てるため、地方税法に基づき課税する目的税です。
市内に住んでいる方で、各職場の医療保険(健康保険、共済組合、船員保険など)や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方以外は、国保に加入しなければなりません。
国保税は個人課税ではなく世帯課税です。そのため世帯主が納税義務者となります。世帯主が国保に加入していなくても、その世帯に国保加入者がいる場合は、その世帯主が納税義務者となります。
※「令和7年度国民健康保険税のしおり」は以下よりダウンロードできます。
![]() 令和7年度鶴岡市国民健康保険税のしおり
(PDF:805KB)
令和7年度鶴岡市国民健康保険税のしおり
(PDF:805KB)
◆令和7年度の改正内容
| 内訳 | 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|---|
| 課税限度額 | 医療保険分 |
650,000円 240,000円 170,000円 |
660,000円 260,000円 (改正なし) |
※1世帯の最高課税額は109万円(介護保険分なしの世帯は92万円)となります。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
7割軽減基準所得額 |
43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1) | (改正なし) |
| 5割軽減基準所得額 | 43万円+(29万5千円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1) | 43万円+(30万5千円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1) |
| 2割軽減基準所得額 | 43万円+(54万5千円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1) | 43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1) |
※被保険者数には「特定同一世帯所属者」を含みます。詳しくは後述「税の軽減(基準より所得の少ない世帯)」をご覧ください。
※給与・年金所得者の数 : 世帯主及び被保険者のうち、給与又は公的年金の所得のある方の人数
◆令和7年度国保税額の計算方法
| 内容 | 計算方法 | |
|---|---|---|
1.所得割額 |
加入者全員の前年中の所得に応じて課税 |
「(前年中の総所得金額等 ※ -基礎控除最大430,000円)×7.5%」を加入者ごとに計算した合計額 |
2.被保険者均等割額 |
加入者の人数に応じて課税 |
「被保険者(加入者)数×25,200円」(年額) |
3.世帯別平等割額 |
加入世帯に一律に課税 |
一世帯あたり18,400円(年額) |
内容 |
計算方法 |
|
|---|---|---|
1.所得割額 |
加入者全員の前年中の所得に応じて課税 |
「(前年中の総所得金額等 ※ -基礎控除最大430,000円)×2.7%」を加入者ごとに計算した合計額 |
2.被保険者均等割額 |
加入者の人数に応じて課税 |
「被保険者(加入者)数×8,400円」(年額) |
3.世帯別平等割額 |
加入世帯に一律に課税 |
一世帯あたり7,200円(年額) |
内容 |
計算方法 |
|
|---|---|---|
1.所得割額 |
介護保険第2号被保険者全員の前年中の所得に応じて課税 |
「(介護保険第2号被保険者の前年中の総所得金額等 ※ -基礎控除最大430,000円)×2.2%」を加入者ごとに計算した合計額 |
2.被保険者均等割額 |
介護保険第2号被保険者の人数に応じて課税 |
「介護保険第2号被保険者(加入者)数×10,800円」(年額) |
3.世帯別平等割額 |
介護保険第2号被保険者の世帯に一律に課税 |
一世帯あたり5,200円(年額) |
※総所得金額等 : 原則として、住民税で課税対象となる所得ですが、一部の所得の取扱いや繰越控除の適用において住民税とは異なります。
- 世帯に介護保険第2号被保険者がいない場合は、医療保険分の合計額と後期高齢者支援金等分の合計額を合算した額(100円未満切捨て)となります。
- 医療保険分の課税限度額は66万円、後期高齢者支援金等分の課税限度額は26万円、介護保険分の課税限度額は17万円です。
◆所得割額の計算対象となる所得の種類及び取扱いについて
・利子所得(分離課税の適用を受けるものを除く)
・配当所得(分離課税の適用を受けるものを除く)
・不動産所得
・事業所得(営業所得、農業所得等)
・給与所得 ※1
・雑所得(公的年金所得等) ※2
・総合課税分の短期譲渡所得
・総合課税分の長期譲渡所得(2分の1に相当する金額)
・一時所得(2分の1に相当する金額)
・山林所得
・分離課税分の土地建物等の短期譲渡所得(特別控除後)
・分離課税分の土地建物等の長期譲渡所得(特別控除後)
・(申告分離課税を選択した)上場株式等にかかる配当所得等 ※3
・(申告分離課税を選択した)上場株式等にかかる譲渡所得等 ※3
・一般株式等にかかる譲渡所得等
・先物取引にかかる雑所得等
※1:給与所得と年金所得の両方がある方は、給与所得の金額から10万円を限度に控除します。(所得金額調整控除)
※2:障害年金や遺族年金などの非課税年金、その他失業給付などの非課税の収入は、計算に含みません。
※3:確定申告をされる方が、住民税が特別徴収された上場株式等の配当所得等及び源泉徴収口座内の上場株式等譲渡所得について申告されない場合、これらの所得は住民税の総所得金額に含まれないため、国民健康保険税の所得割額の算定対象になりません。しかし、損益通算や繰越控除、各種控除等の適用を受けるために確定申告をした場合は、住民税の総所得金額に含まれるので、国民健康保険税の所得割額の算定対象になります。
・退職所得を一括で受け取る場合は、計算に含みません。ただし、退職金を年金の形で受け取る場合は雑所得として扱い、計算に含みます。
・事業主の場合、営業所得や農業所得などは、専従者給与を控除した後の額が計算の対象となります。
・基礎控除は最大43万円です。住民税で適用される扶養控除や医療費控除、雑損失の繰越控除等はできませんが、純損失の繰越控除は可能です。
◆税の軽減(基準より所得の少ない世帯)※申請は不要です。
- 世帯の年度当初の加入日における被保険者数と、世帯主及び被保険者の軽減判定所得額の合計金額により軽減に該当するか判断します。
- 世帯主が国保に加入していなくても、世帯主の所得も含めて判定し、被保険者均等割額と世帯別平等割額の金額を軽減します。世帯に特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度に移行する直前の医療保険が国保で、かつその前後で世帯主が同じ方)がいる場合は、その人数と所得も含めて判定します。
- 軽減判定所得額は、下記の所得の合計額です。所得割額の計算対象とは一部取扱いが異なります。
・利子所得(分離課税の適用を受けるものを除く)
・配当所得(分離課税の適用を受けるものを除く)
・不動産所得
・事業所得(営業所得、農業所得等)
・給与所得 ※4
・雑所得(公的年金所得等) ※5
・総合課税分の短期譲渡所得
・総合課税分の長期譲渡所得(2分の1に相当する金額)
・一時所得(2分の1に相当する金額)
・山林所得
・分離課税分の土地建物等の短期譲渡所得(特別控除前)
・分離課税分の土地建物等の長期譲渡所得(特別控除前)
・(申告分離課税を選択した)上場株式等にかかる配当所得等 ※6
・(申告分離課税を選択した)上場株式等にかかる譲渡所得等 ※6
・一般株式等にかかる譲渡所得等
・先物取引にかかる雑所得等
※4:給与所得と年金所得の両方がある方は、給与所得の金額から10万円を限度に控除します。
※5:障害年金や遺族年金などの非課税年金、その他失業給付などの非課税の収入は、計算に含みません。
※6:確定申告をされる方が、住民税が特別徴収された上場株式等の配当所得等及び源泉徴収口座内の上場株式等譲渡所得について申告されない場合、これらの所得は住民税の総所得金額に含まれないため、国民健康保険税の所得割額の算定対象になりません。しかし、損益通算や繰越控除、各種控除等の適用を受けるために確定申告をした場合は、住民税の総所得金額に含まれるので、国民健康保険税の所得割の算定対象になります。
・事業主の場合、営業所得や農業所得などは、専従者給与を控除する前の額が計算の対象になります。
・事業主から専従者給与を受け取った場合、その給与所得は計算に含みません。
・基礎控除最大43万円を適用する前の金額が計算の対象となります。
・純損失及び雑損失の繰越控除が可能です。ただし、純損失の繰越控除額は、確定申告上の「本年分で差し引く繰越損失額」とは別に計算します。分離課税分の損失は、分離課税分の所得に対してのみ繰越控除が可能です。
・昭和35年1月1日以前の生まれの方(65歳以上の方)の公的年金所得は、税法上の公的年金控除とは別に15万円を差し引いた後の金額で計算します。
- 医療保険分、後期高齢者支援金等分、介護保険分ともに次の所得金額の世帯に対し、被保険者均等割額は加入者一人につき各割合、世帯別平等割額は平等割額の各割合が軽減されます。
| 割合 | 要件 |
|---|---|
| 7割軽減 | 軽減判定所得が43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の世帯 |
| 5割軽減 | 軽減判定所得が43万円を超え、その金額が 43万円+(30万5千円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の世帯 |
| 2割軽減 | 軽減判定所得が43万円を超え、上記以外でその金額が 43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の世帯 |
※所得税又は市県民税の申告義務のある被保険者及び世帯主が申告をしていない場合、軽減判定を行えませんので、必ず申告してください。
◆税の軽減(未就学児)
- 子育て世代の経済的負担軽減の観点から、未就学児の被保険者均等割額を一定割合減額します。
軽減世帯以外 |
2割軽減世帯 | 5割軽減世帯 | 7割軽減世帯 |
|---|---|---|---|
| 16,800円 | 13,440円 | 8,400円 | 5,040円 |
※国保に加入する全世帯の未就学児(平成31年4月2日以降生まれ)が対象
※1人あたりの年額33,600円(医療保険分25,200円+後期高齢者支援金等分8,400円)を半分に減額
基準より所得の少ない世帯(2割・5割・7割軽減世帯)の場合は、軽減適用後の金額を半分に減額
◆税の軽減(産前産後)
- 子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産予定もしくは出産した国民健康保険被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割額及び被保険者均等割額を免除します。
免除対象期間
・単胎妊娠:出産予定日又は出産日の属する月の前月から翌々月までの4か月間
・多胎妊娠:出産予定日又は出産日の属する月の3か月前から翌々月までの6か月間
※出産予定日又は出産した日が令和5年11月1日以降である方が対象です。
※令和5年度は、令和6年1月以降が免除対象月となります。
※軽減を受けるには原則、国保年金課又は各地域庁舎市民福祉課(朝日庁舎は地域づくり推進課)での申請が必要です。
詳しくは、産前産後期間の国民健康保険税の免除制度について をご覧ください。
◆税の軽減(会社都合の退職又は正当な理由のある自己都合退職)
- 次に該当する方について、失業時から翌年度末までの間、前年の給与所得を70%減額した所得額で計算します。
(1)雇用保険の特定受給資格者(「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」離職理由コード 11.12.21.22.31.32の方)
(2)雇用保険の特定理由離職者(「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」離職理由コード 23.33.34の方)
※離職時点で65歳未満の方が対象です。軽減を受けるには、国保年金課又は各地域庁舎市民福祉課(朝日庁舎は地域づくり推進課)での申請が必要です。
◆激変緩和措置
- 国保から後期高齢者医療制度に移行する被保険者がいる場合、国保税の負担が急に増えることがないように、次のような軽減を受けることができます。
(1)所得の少ない世帯に対する国保税の軽減について
軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。
(2)世帯別平等割額の軽減について
国保から後期高齢者医療制度に移行することによって、国民健康保険の被保険者が1人となる場合には、移行した月から5年間は2分の1、その後3年間は4分の1、世帯別平等割額を減額します。
◆旧被扶養者減免
- 75歳以上の方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳から74歳までに限ります)が新たに国民健康保険に加入する場合、次のような軽減を受けることができます。
(1)被保険者に係る所得割額が賦課されません。
(2)被保険者均等割額が半額になり、さらに被保険者が1人の場合には世帯別平等割額が半額になります。(資格取得日の属する月から2年間)
◆納付について
- 普通徴収:7月から翌年3月までの毎月、年9回の納期になります。各期別の税額については、年税額を納付回数で均等に割った後、1,000円未満の端数が生じた場合は、その金額を最初の納期額に合算します。
- 特別徴収:年金の支給月(4・6・8・10・12・2月)に差し引かれます。年金から徴収される方は、次のいずれにも該当する方です。
(1)世帯主が国民健康保険税の被保険者となっていること
(2)世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること
(3)特別徴収の対象となる年金(例:老齢基礎年金)の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
※年金からの特別徴収については、申出によって口座振替による納付に変更することができます。納付書払への変更はできません。
- 年度の途中で加入・脱退した場合は、国保税額を月割りで再計算します。また、遅れて届出した場合も、さかのぼって計算します。したがって届出により税額が変更になる場合であっても、変更後の「国民健康保険税納税通知書兼変更・決定通知書」が送付される前に到来する納期分については、お手元の納付書で納付してください。
- 特別な事情(災害、病気、事業廃止など)がなく、国民健康保険税を滞納した場合、国民健康保険法等の規定により、滞納の状況に応じて、一旦、医療費の全額を支払い、後日申請により自己負担分を除いた額を払い戻す「特別療養費の支給」となる場合があります。
- 国民健康保険税の納付が困難な事情がある場合は、未納のままにせず、納付方法などについてご相談ください。
*納付方法についての相談先 : 納税課納税係(0235-35-1182)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Readerのダウンロードページへ
Adobe Readerのダウンロードページへ
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071