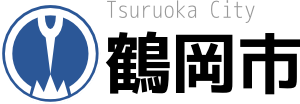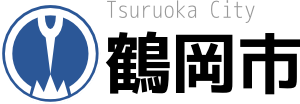国民年金は、加入者の老後の生活や、障害を負ったときなど、もしものときに備え、生活の安定がそこなわれることがないように、生活の維持・向上のため、国の負担と納めた保険料によって、国民全体でお互いを支えあう国の年金制度です。
国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての方が加入することになります。加入・脱退の手続きは忘れずに済ませるようにしましょう。
■■20歳になると加入します
国民年金の被保険者(加入者)は、第1号から第3号被保険者に区分され、いずれも国民年金法上の被保険者になります。
20歳になる方で、第2号被保険者・第3号被保険者以外の方には、日本年金機構から国民年金加入のお知らせをお送りしています。
■■こんなときは届出が必要です
加入者の就職・退職・結婚などによって、年金の加入種別に変更があったときは、勤務先の事業所または市役所へ届出が必要になります。
国民年金第1号被保険者への変更手続きを郵送でする場合は、国民年金被保険者関係届出書(申出書)を記入し、退職日(扶養でなくなった日)のわかる書類・本人確認書類(顔写真付きの身分証明書、もしくは保険証と基礎年金番号が分かるもの)のコピーを添付して、鶴岡市役所国保年金課国民年金担当へ送付してください。
■■国民年金保険料の納付について
国民年金第1号被保険者になると、日本年金機構から納付書が送付されます。
令和7年度の国民年金保険料は1万7,510円(月額)で、金融機関やコンビニエンスストア、またはスマートフォンアプリ(AEON Pay、auPAY、d払い、PayB、PayPay、楽天ペイ)で納付できます(市役所、年金事務所では納付できません)。
また、口座振替やクレジットカード納付、前納制度を利用すると納め忘れがなく便利です。
前納制度を利用すると、保険料が割引されます。
■■将来の老齢基礎年金の額を増やす付加保険料とは
国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、定額の保険料に月額400円の付加保険料を納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。
加算される金額は、(200円×付加保険料納付月数)で、年額の年金額に加算されます。2年以上受給すると、掛けた付加保険料分以上の年金額を受け取ることができるため、お得と言えます。
なお、付加保険料の納付は申出月からの開始となります。
ただし、次の方は付加保険料を納付することができません。
・国民年金保険料の納付を免除または猶予されている方(学生納付特例も含みます)
・国民年金基金に加入されている方
個人型確定拠出年金の納付額によっては、付加保険料と併用できない場合があります。
付加保険料の納付をやめたいときは、市役所やお近くの年金事務所へ申出をすることで、申出をした月の前月から、付加保険料を納付する方でなくなります。
■■国民年金保険料を納めるのが難しい方は
失業などの経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合、所得審査により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
2年1ヵ月前の保険料分まで、保険料の免除や猶予の申請ができます。
免除や猶予が承認されると、納付した場合に比べて、将来受け取る年金が少なくなります。
ただし、免除や納付猶予された期間の保険料は10年以内であれば後から納めること(追納)ができます。なお、免除等を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は加算金がつきます。
申請や問い合わせは鶴岡年金事務所及び市役所国保年金課国民年金担当(9番窓口)または各地域庁舎市民福祉課(朝日庁舎は地域づくり推進課)で受付します。
免除制度(全額免除、一部免除)
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合、保険料の全額、4分の3の額、半額または4分の1の額がそれぞれの基準で免除されます(学生は学生納付特例制度の対象)。
なお、一部免除については、免除額を除いた保険料を納付しないと一部免除が無効(未納と同じ扱い)になりますので、ご注意ください。
納付猶予制度
20歳以上50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます(学生は学生納付特例制度の対象)。
学生納付特例制度
20歳以上の国民年金加入の学生で、前年所得が一定額以下など基準に該当する方は、在学中の保険料納付が猶予されます。
※退職・失業による特例について退職または失業した方は、申請の際にハローワークの確認印のある雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証や雇用保険受給資格通知(いずれもコピー可)をお持ちください。なお、令和元年10月30日以降に、同一の失業等を理由として、上記失業に関する証明書類を提出して申請済みである方は、再度の添付は不要ですので、窓口にてお申し出ください。
※申請年度の申告が済んでいない場合は、審査ができませんので、申告をした上で免除を申請してください(配偶者、世帯主も同様)。
国民年金保険料免除・猶予制度の詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
■■国民年金にはこんな給付があります
国民年金の給付には以下のものがあります。
申請や問い合わせは市役所国保年金課国民年金担当(9番窓口)または各地域庁舎市民福祉課(朝日庁舎は地域づくり推進課)で受付します。
なお、老齢基礎年金の手続き先について、年金加入期間が国民年金(第1号被保険者)のみの方は市で受付しますが、それ以外の方はお近くの年金事務所での受付となります。
老齢基礎年金
保険料を納めた期間などの受給資格期間が10年(120月)以上ある方が、原則として65歳から受け取る年金です。
20歳から60歳に達するまで40年間(480月)保険料を納めた方の令和7年度の支給額(年額)は83万1,700円になります。
障害基礎年金
病気やけがで体に障害が残った場合、一定の支給要件を満たしていれば、障害基礎年金が受け取れます。令和7年度の障害基礎年金の支給額(年額)は以下のとおりです。
1級 103万9,625円+子の加算2級 83万1,700円+子の加算※子の加算額は、同一生計の子(18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級、2級の障害がある子)がある場合に加算されます。
遺族基礎年金
夫または妻が死亡した場合には同一生計の子のある妻または夫、父または母が死亡した場合には同一生計の子が遺族基礎年金を受け取れます(一定の支給要件あり)。令和7年度の遺族基礎年金の支給額(年額)は83万1,700円+子の加算額です。
※子の加算額は、同一生計の子(18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級、2級の障害がある子)がある場合に加算されます。
このほか、国民年金の独自給付として、寡婦年金、死亡一時金、短期在留外国人の脱退一時金があります。
詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
鶴岡年金事務所に相談する場合注意:年金相談は予約制となります。
【予約】
ねんきんダイヤル:0570‐05‐4890
鶴岡年金事務所 電話:23‐5040 ※予約受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分
【相談時間】
月曜日(休日の場合は火曜日) 午前9時から午後6時
火曜日から金曜日 午前9時から午後4時
第2土曜日(完全予約制) 午前10時から午後3時
詳しくは、次の日本年金機構ホームページをご覧ください。
■問い合わせ
国保年金課
電話:0235-35-1294
FAX:0235-24-9071