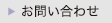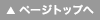企画展関連インタビュー
開館15周年記念企画展〈『喜多川歌麿女絵草紙』の世界―歌麿と蔦重―〉の展示では、『喜多川歌麿女絵草紙』にも触れられている、作家高橋克彦氏へのインタビュー(第5回企画展〈藤沢周平と浮世絵〉図録に掲載)の一部を紹介しています。企画展の開催期間中限定で、高橋克彦氏のインタビューの全文を公開します。
公開期間 令和7年3月28日(金)~ 9月23日(火)
インタビュー「藤沢周平の浮世絵師たち」 高橋克彦(作家)
―― 藤沢さんと浮世絵の話をきちんとしてみたかった ――
藤沢さんとの縁僕の小説家として初めての単行本『写楽殺人事件』の帯は藤沢周平さんと井上ひさしさんに書いていただいているんです。担当してくれた講談社の中澤(義彦)さんという編集者の尊敬する作家が、藤沢さんとひさしさんだったんです。僕は、お二人に帯を書いていただくなんて、恐れ多いことだと思ったんだけれども、「藤沢さんだったら浮世絵が好きだから、絶対書いてくれますよ」というのでお願いして、推薦文をいただけたんです。昭和五十八年(一九八三)のことですね。
それから三年後、吉川英治文学新人賞を、僕が『総門谷』で頂戴したとき、吉川英治文学賞の受賞者が藤沢さんとひさしさんだった。あれはびっくりしました。受賞者の控え室で、藤沢さんとひさしさんに紹介されたのが、藤沢さんとお会いした最初ですね。
作家デビューしてまだ三年。吉川英治文学賞といったら、物書きのもらえる一番上の賞ですよ。それを受賞されたお二人に「一緒に並んで話しましょう」って言われても、並べないですよ。
そうしたらね、次に直木賞を『緋(あか)い記憶』でいただいたとき、藤沢さんとひさしさんが選考委員だったんです。当時の選評を見ると、一番褒めてくださっているのは、ひさしさんと藤沢さん。直木賞の授賞式には藤沢さんもいらして、控え室でいろんなお話を伺いました。だから、ものすごい縁を感じますよ。
ひさしさんは、その後、盛岡に講演でいらっしゃるなど、打ち解けていく機会がありましたが、藤沢さんは、授賞パーティー以外めったに出て来られない方だったでしょう。それで親しくお付き合いする機会がなかったんです。
でもね、僕の物書き人生の中で、スタートとか転換点には必ず藤沢さんがいらっしゃったなというイメージがあります。
浮世絵師の眼
藤沢さんと僕は、昭和二年生まれと昭和二十二年生まれだから、ちょうど二十歳違い。藤沢さんが『溟い海』でオール讀物新人賞を受賞なさった四十三歳のとき、僕は二十三歳。こっちはホラーなんか書いていて、時代小説を書くとは全く思ってもいなかった。その当時(昭和四十六年頃)は、浮世絵の画集などがたくさん出版された頃で、文芸の世界でも浮世絵ブームがあったんですよ。浮世絵はずっと好きだったから、南原幹雄さんの『女絵地獄』や、笠原良三さんの『小説歌麿』を読んでいて、「浮世絵が小説のテーマになりうるんだな」と思ってはいました。
藤沢さんがデビューなさったあたりは、浮世絵が文化人の関心を集めていた時代だったんです。展覧会も頻繁にあって、浮世絵専門のリッカー美術館が開館した頃でもあり、その美術館のある銀座の画廊などを見てまわると、浮世絵にたくさん触れることができました。
その辺りは、僕もしょっちゅう行ってたから、もしかすると、藤沢さんとすれ違っていたかもしれない。
いま改めて『溟い海』を読みますと、僕が四十三の頃を考えてしまいます。このような作品を同じ歳で書けたかなというと、非常に難しい。
つまりね、藤沢さんの小説って何だかちょっと変わっているんです。それまでの浮世絵師をテーマにした小説は「浮世絵師とは何者であるか」とか「浮世絵師の人生」を書いているものが多いんですね。『溟い海』は、北斎が主人公だけれども、彼がどう絵を描くのか、何を描いたかということはあまり書いていないんです。藤沢さんは浮世絵師を書きたかったのではなくて、浮世絵師の眼が欲しかったんだなと感じました。
その思いが、ずっと僕の中にあったので、「あ、やっぱり自分の見方は間違ってないな」と『喜多川歌麿女絵草紙』を読んで思いました。
これは、物書きとしての推測になるのですが、『喜多川歌麿女絵草紙』は、藤沢さんに、新しい視点を与えたと思うんですよ。藤沢周平という眼で見て女を描くのと、歌麿の眼で見る女って違うんです。藤沢さんが歌麿の眼になって女たちを見たことによって、今まで書かれてきた世界とは違うものになったと思うんですよ。その眼を会得したから、もっと違うものを書けていくようになったというかね。
それまでは、やはり藤沢周平という眼があったと思いますね。歌麿については北斎や広重ほど人物の説明や絵についても書き込んでいない。北斎や広重を描いたときとは違うものを感じます。
『喜多川歌麿女絵草紙』の場合は、歌麿の目の前に登場してくる女性たちの暗部を書くための、それを見届けるための眼鏡として歌麿を必要としていたんじゃないのかという感じがしますね。
エッセイで、次は写楽ですかという話があったとき、「べつに急ぐ必要はないだろうと思う」とおっしゃっているけど、写楽の眼を別に欲しがっていないですよ。歌麿の眼を手に入れちゃったから、もう充分、というかね。
大変な創作の秘密を話しているような気がしてきました(笑)。
説明しない勇気
ひさしさんの主人公は輪郭がすごく明確に見えてくるけれども、藤沢さんの場合は、輪郭があまり見えてこないんです。
ひさしさんはまず徹底して調べて、頭の中で形になるまで我慢して書かずに、そして一気に出す。藤沢さんも同じように作り込むんだけれども、できたものをふっと手放す人だと思うんです。歌麿ができたときにふっと手放して、眼だけを使うみたいにね。ひさしさんは、俯瞰(ふかん)で書くんですよね。藤沢さんは物語の中に立っている人から見る。藤沢さんは輪郭を取っぱらって、できた着ぐるみの中に入ってしまうような。たぶんそれが違いなんだと思います。作風の違いというか。
『喜多川歌麿女絵草紙』を読んだら、読者は歌麿ってどういう人なんだろうと、興味を持ちますよね。そこを見事に説明しない。あれは途方もない勇気ですよ。
あいまいな存在の絵師たちの目線を自分のところに引っ張ってくる。きっとね、藤沢さんは浮世絵師が好きだったんじゃないかな。北斎とか、広重とか、歌麿みたいな、江戸の市井にいた人たちが。非常に印象的だったのは、歌麿が町を歩くのが好きだと言って、両国あたりからずっと歩き続けるけれども、ああいうことは歌麿の資料のどこにもないわけ。あれは藤沢さんが歌麿になっているんですよ。だから、広重に化けたり、北斎に化けたり。僕が最近書いた歌麿のなかでもね、歌麿の気持ちを相当深く書いたつもりでいるんだけれども、実をいうと歌麿じゃないんです、私なんです。読む方は歌麿の心理だと思って読んでだまされちゃうんです(笑)。
ちょうど歌麿の話を書いたばかりだったから、このインタビューの話をいただいて藤沢さんの作品を読み返すのは、おもしろかったですよ。「自分だったらこう書く」ということを、もう書いているわけだから。
僕は「歌麿はどういう人間か」ということを書きたくて書くけれども、藤沢さんはそうじゃないんですよね。「歌麿はどういう人間か」っていうことよりも、「歌麿ならどう思うんだろう」という眼で世界を見ようとしている。そこが、決定的に違うところですよ。
写楽をものすごく印象的に書いています。蔦屋(つたや)が、ついさっきすれ違ったのが写楽だよと言うじゃないですか。「どういう男ですか」って質問させて、蔦屋に藤沢さんの写楽像を語らせてもいい場面です。読者も当然興味を持っている。物語の中で、写楽は口下手だから女を通訳みたいに連れて来ているんだと書いたということは、藤沢さんが写楽像をつかんでいるからなんです。つかんでいないと、ああいう描写はできない。藤沢さんの中には、写楽ってこういう人間で、こういう環境で、こういう暮らしをしているというのが、はっきり頭にあった。だから、例えばあそこで歌麿が「写楽ってのは一体どういう男なんですか」と言ったら、蔦屋は答えられるはずなんです。なのに書かない。それがすごい。あれはびっくりした。僕は「これはどういうことなんだろう?」と。あそこでね、破綻がないのは、歌麿が写楽の絵に興味はあるけれども、人には興味がない、だから聞かなくてもいいんですよね。そこらへんのさじ加減がうまい。
馬琴にしても深入りしていないです。馬琴がそのとき何を考えていたかを会話でしかやらない。完全に歌麿の目線だからそうなる。例えば、僕が馬琴を出すと、深入りさせるし、江戸のおもしろさ、あの時代のおもしろさみたいなのを書こうとするはずです。でも、藤沢さんの歌麿は、毅然として歌麿の眼からぶれないから、書かない。歌麿を自在に動かしているということですよね。だから、時代そのものを書こうとはしていない。
ところが、作家の性(さが)といいますか、われわれは時として主人公が自分の眼ではみられないところを書いてしまうんですよ。藤沢さんはそこの見極めがきちんと、できた方だったんでしょうね。
藤沢さんの発明
『喜多川歌麿女絵草紙』「赤い鱗雲」で、歌麿が描いている女が、盗賊の一人とそれと知らず付き合っている。二人が会うことを歌麿が岡っ引に教えたことで男が捕まってしまう。次に女と会ったとき「知っていらしたんでしょ、先生」という一言がある。あれだけで、そのセリフの持っている意味を書かない。作家が百人いたら九十九人の作家は書きますよ。
『溟い海』で、広重をいたぶってやろうと待ち構える北斎が、広重の陰惨な表情を見てやめる場面がありますよね。広重の表情は人生で絶望的な躓(つまず)きがあったからだろうとは書いても、それが「何か」は書かないんです。『旅の誘い』では、英泉が広重「東海道五十三次 蒲原」を評して、「一度は人生の底を見た人間でないと、ああいう絵は出て来ねえな」と言う。でも、広重の人生のどん底が何であるかを書かない。物書きとして投げているんじゃないんですよ。わざと書いてない。それが藤沢さんのすごいところ。改めて読み直してみると、常に藤沢さんは「人っていうのは分からないところがあるけれど、それはそれでいいじゃないか」と、あえて書いていない。誤解されると困りますが、藤沢さんが踏み込んでいないということではないんです。歌麿の心情にすごく踏み込んでいるんだけれども、結局のところ人の心は分からないということなんですよ。これほど人生の裏表が分かっている歌麿ですらこの女は分からないというから、はじめて読者は納得するんです。
歌麿が話しているように、長年連れ添ったおりよでも、本当のところは分からない。それは、読者一人ひとりが、みんな抱えている人生の奥深さだと分かっているんですよ。僕は美術から入ったせいかもしれないけれども、読者にも自分と同じ景色が見えないとつらいんですよ。僕は常に、小説の舞台を見えるように書くわけです。でも藤沢さんは、たぶん、見えなくてもいいという考え方ですよ。あれだけ花とか桜とかすばらしい情景を書きながら、人間の心はすべては見えてなくてもいいという突っぱね方。
そこまで踏み込む必要が、たぶんないと思ったんじゃないですか。踏み込んでしまうと、自分ひとりの物語になるけれども、その前で止めると普遍的な物語になるんです。だから、介護が大変で親を殺したというと、それはすごく特定されたどん底になるけれども、親で苦労させられたというところで終わると、普遍性がでてくる。その塩梅(あんばい)というのが、実によく分かっている人なんだと思いました。
だから、『溟い海』を書かれるまでの藤沢さんの心の奥にあった人生のどん底っていうのが気になりますよね。
『浮世絵師』のときには、北斎と女性が怪しげな関係になっていくじゃないですか。たぶん、あれが書きすぎたと思った部分だろうと思うんです。『溟い海』のときには女性との関係を遠巻きにしていますよね。それによって、作品が活きていくという、物書きとしての勘ができたんだと思います。だから藤沢さんの小説って、どろどろしそうなところにいきそうで、踏み込んでいかない小説が多いんですよね。そこまで書いちゃうと違うなっていうのが、勘としてあるんではないですかね。
いや、この歳になって勉強させられたなとつくづく思ってます(笑)。
SFとかホラーとかミステリーを書いているとね、明解にイメージが伝わるような小説じゃないと書いていて不安なんですよね。自分の書いている世界が一人ひとりの読者にきちんと伝わっているんだろうかと思うと不安で。
謎解きが前提として常にあるでしょう。だから、どんな小説を書いていても、一人の人が苦しんでいると、なぜ苦しんでいるのかとか、どうすればその苦しみから脱却できるのかとか、必ず小説の中に盛り込もうとするんですね。
人の心は分からないというところで、突っぱねてそれを通したというのが、藤沢さんの小説家としての発明かもしれませんね。
世界をまるごとつかまえる
藤沢さんの小説を読んでいると、画集だけでは手に入らない知識をたくさん持っていらっしゃることが窺(うかが)えるんです。物書きは研究者より詳しくなければならないんです。研究者は目の前にある絵と向き合っていればいいけれども、小説を書くということは、世界をまるごとつかまえないといけないですからね。藤沢さんが浮世絵に興味を持っていた四十年前には、版元がどういう状況にあったかとか、そのときの時代背景がどうであったかといった研究はなかったんですよ。私が『写楽殺人事件』を書いたころから、ようやく絵師の研究だけでなく、背景を含めた研究が広がっていったと思います。藤沢さんは、ご自分で江戸の版元の出版情報だとか、町並みだとかを調べられたんだと思います。
例えば「蒲原」。広重が見たとされた蒲原は夏の風景なんです。雪景色は見ていない。奥にコタツみたいな山がありますよね。現地に行って見たんですけど、向きが違うんです。藤沢さんも知っていたと思いますよ、当時の画集にはちゃんと書いていますから。それを読んでいて敢えてそこに触れない。そこまで踏み込む必要がたぶん藤沢さんにはなかったんでしょうね。
北斎は削り取っていく絵師なんです。藤沢さんも書かれているけど、富士山の皮を剝ぎ取っていくようにね。どんどん削っていって、対象を極めていく。広重はどちらかというと、絵のために足しながら、絵をこしらえていく。雪を剝ぎ取って夏の風景に変えるのは簡単でも、夏に見たものに雪を重ねるのは大変なことですよ。じゃあ「蒲原」でそうやっていろんなものを変えて一体何を表しているかというと、深い悲しみであったりする。広重の絵に藤沢さんが惹かれたのは、小説も、そういうものだって気付かれたからじゃないですかね。
お千代という女性が『喜多川歌麿女絵草紙』にでてきますよね。あれは、歌麿門人の千代女という、数冊の黄表紙の挿絵しか作品を残していない不思議な人物なんです。歌麿の弟子の系図に出てくるぐらいで、研究書を相当深く読み込んでいないとまず知らない名前です。どのような形で歌麿の弟子になって、どのようにして消えていったのか、資料がないから分からないんですよ。歌麿の出自にしても母親が早く死んだとか、子供の頃に男の影があって、それが鳥山石燕じゃないかと思ったことがあるとか、さらっと書いている。本当に歌麿の伝記などもたくさん読んでいるなと思いますね。
そこまで膨らませるというのは、藤沢さんがよっぽどのめり込んでいないと書けないですよね。それでいながら、絵や絵師について、例えば歌麿が「青楼の画家」だったとか、不思議なぐらいに代表作については述べていない。
僕の場合は『だましゑ歌麿』で延々と作品についての解説を書きましたからね。
『喜多川歌麿女絵草紙』を読んでいても、あそこまで調べていたら、このとき歌麿が描いている絵はこれであったと、書きそうなもんなんですよ。それを全くしていないから、藤沢さんはものすごく浮世絵を愛しているけれども、歌麿の人生を描こうとしたんではないなと思いました。
決して歌麿の眼から外れない。そこがやっぱり、研究者の眼からみるともったいない。同じ作家からみるとすごく思い切った覚悟というものを感じます。
僕の「完四郎広目手控」シリーズは、藤沢さんが『江戸おんな絵姿十二景』でやられたようなアイデアを出版社からもらって、書き始めた物語なんです。広重の「名所江戸百景」の中から二枚選んで、二枚の絵に描かれた場所をつなぐ。ミステリーに仕立てるのは、大変だけれども、すごくおもしろい作業ではあるんですよ。その作業が楽しくて完四郎シリーズは、今も続いているんです。
『江戸おんな絵姿十二景』の単行本や文庫本に雑誌では掲載されていたモチーフの浮世絵が載っていないのは残念ですね。一つひとつの物語をみると、タイトルから想像つくものもあるけれども、絵がないとただの物語を読むのと一緒でね。なぜ、藤沢さんが、この絵のどこに興味をひかれて、そこからどう物語を紡ぎだしてきたかということが伝わってこないですから。やはり藤沢さんを読み解く上で、絵があるのとないのとでは全然違います。
こうしてみると、藤沢さんと浮世絵の話をきちんとしてみたかったという気がしますね。
高橋克彦(たかはし かつひこ)
 昭和22年(1947)、岩手県釜石市生まれ。
昭和22年(1947)、岩手県釜石市生まれ。昭和58年『写楽殺人事件』で江戸川乱歩賞、昭和61年『総門谷』で吉川英治文学新人賞、 昭和62年『北斎殺人事件』で日本推理作家協会賞、平成4年『緋い記憶』で直木賞、 平成12年『火怨』で吉川英治文学賞を受賞。 『竜の柩』『炎立つ』『時宗』『完四郎広目手控』『天を衝く』『ゴッホ殺人事件』など著書多数。浮世絵研究家として『浮世絵鑑賞事典』『浮世絵ミステリーゾーン』『江戸のニューメディア』『浮世絵ワンダーランド』などの著書がある。