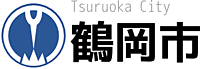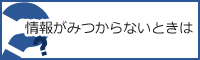旧町名とその由来3
更新日:2015年1月14日
近郊の村
大宝寺
中世には、今の鶴岡を大宝寺と称していた。最上氏の時代に
京田
鶴岡城下の北に位置し、京田のつく10集落がほぼ一直線に並んでいる。地名については(1)羽黒山の経田説、(2)武藤氏時代の家臣への給田説、(3)京都へ運ぶ米を作っていた所という説がある。江戸時代には羽黒山の領地1,800石余りの内半分が平京田・北京田・小京田にあり、それに限って経田と書いていた。明治22年に平京田(村)・西京田(村)・北京田(村)・中野京田(村)・覚岸寺(村)・林崎(村)・荒井京田(村)・高田(明治9年高田麦村を改称)・安丹(同年千安村と丹波興屋村が合併)・福田(同年論田村と阿部興屋村が合併)・豊田(同年野興屋村と漆島村が合併)の11ヶ村が合併して京田村となったが、昭和30年に鶴岡市に編入された。
道形
江戸時代始めに開発された村で、当時の資料には「堂形新田村」と記されている。明治22年の町村制の施行により道形村は、大宝寺村大字道形となった。現在は町名として残っている。
茅原
鶴岡城下の北にある農村で茅原村といった。村ができる前は、
新形
鶴岡城下の北に接する農村で新形村といった。最上氏時代までは今の若葉町あたりに舞台村と一ヶ所にあったが、酒井氏の町割により分離し現在地に移住させられた。明治22年の町村制施行により大宝寺村に編入、大正9年鶴岡町の大字となる。現在は町名として残っている。
新斎部
鶴岡城下の西に接し、江戸時代には新町村・齋藤興屋村・
柳田
鶴岡城下に接する農村で柳田村といった。赤川の旧流路に当たり、付近一帯に川柳が繁茂していたのでこの名がついたともいわれている。明治22年町村制施行のとき稲生村に入り、更に大正7年に鶴岡町の一部となった。
島
鶴岡城下の南及び東に接する農村で島村と称し、島組大庄屋の居宅があった。酒井氏の町割りの際に宅地化し、十三軒町・檜物町などが町割された。村名の由来については、昔この辺一帯を赤川が乱流し所々に島が出来たことによるという説と、最上氏の旧臣の
日枝
鶴岡城下の南に接し、江戸時代は
外内島
鶴岡城下から南へ向かう
遠賀原
鶴岡城下の南に接する農村で、江戸時代には
八ツ興屋
鶴岡城下の東南の集落。その昔、この辺りを赤川が流れていた頃、川岸に鮭を獲るための八軒の小屋が並んでいたが、新田開発が進められ、興屋の字を宛てるようになったと伝えられている。明治22年斎村に編入、昭和30年に鶴岡市の大字となる。
苗津
鶴岡城下の東南に接する農村で苗津村と称した。村名については、
伊勢横内
鶴岡城下の東南、赤川添いに位置する農村で伊勢横内村と称した。村名は、伊勢の
我老林
赤川の西岸に位置する農村で我老林村と称した。村名については、
斎藤川原
赤川の西岸に位置する農村。村名は、その昔赤川の流路に当たっていたことを示す。稲荷村の社人斎藤氏が開発したという伝承もある。明治22年に斎村に編入、昭和30年より鶴岡市の大字となる。
勝福寺
赤川の西岸に位置する農村。勝福寺村と称したが、正福寺・小福寺とも書き、福平村・川上村ともいったという。村名は美田地帯を示す勝福地から転化したという説もある。泉山神社の境内には、鶴岡の古称「
参考にした史料
「
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 市民課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1194
FAX:0235-25-2148