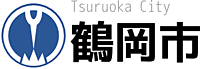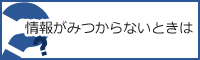黒川の狂言
更新日:2015年1月19日
喜劇的で庶民的な笑いの文学
「狂言」は、日本で最初に成立したせりふ劇であり、ほかに例の少ない笑いの文学と言われています。狂言は能と共に室町時代(1300年代後半~1500年後半の足利氏の時代)に、生まれ育った芸能で、江戸時代(1600年代初頭~1800年半ばの徳川の時代)になると武士の式楽として固定化して古典芸能となりました。
狂言は能と違って、ほとんど面をつけず、素顔のままで演じます。たくましく生きる庶民の姿を描き出している作品が多くあります。その狂言を分類すると、「附子(ぶす)」や「千鳥」のように狂言役者だけで1つのストーリーを演じる“番(バン)狂言(中央では本・ホン)”と「三輪」や「船弁慶」のように、能のなかで役者の一役を演じる“間(アイ)狂言”があります。その多くは前シテと後(のち)シテの中間(中入)に登場し前段から後段へ続く物語の解説などをします。
能と狂言を比べてみると、「能」は悲劇的で貴族的なものと言われますが、それに対して「狂言」は喜劇的で庶民的なものと言われます。狂言役者は、口調や表情、しぐさなどによって、おもしろおかしく筋を展開していきます。
黒川狂言の楽しみ
中央の狂言と黒川の狂言の違いについて25年にわたり黒川能を撮り続けている横浜市在住の写真家、渡部国茂さんにお聞きしました。
「中央の狂言(大蔵流、和泉流のこと以下中央)を見た人が黒川狂言を見ると、幾つかの点で違いを感じると思います。その1つは女性の扮装で、黒川では能と同じように面を付ける点です。中央では美男鬘(ビナンカズラ)という白い布を頭に巻き、余った部分を両耳の所へたらし、直面(ひためん:素顔)で女性を表現します。『節分』という狂言では、女房の役では能と同じように女性の面をつける扮装です。見慣れてくると節分の豆まきも落花生や菓子をまく黒川狂言の方が楽しくなります。男性の扮装では、中央は「肩衣(かたぎぬ)」という裃の上とほぼ同じものを付けますが、黒川は「側次(そばつぎ)」という「法被(はっぴ)」の袖を取った型の衣装を身につけます。
狂言に使う小道具も中央と違っています。『附子』で使う鬘桶(かづらおけ)を黒川では蓋の部分を使いますが、中央では本体部分を使うという点が違っています。
間狂言では『羅生門』や『土蜘蛛』で「きいたか」「きいたか」と2人のアイが登場する黒川独特の形があり、『大江山』では小鬼が間狂言として登場し、これも中央にはない形で楽しめます。
狂言台本は江戸時代に刊行された「狂言記」の系統の台本に近いと言われており、現行の中央のものと微妙な違いが感じられます。
狂言の演目では『三十日囃(みそかばやし)』という黒川独特のものがあり、狂言も黒川で独自に発展したことがうかがえます。庄内弁の味わいのある狂言セリフを聞くのも、黒川狂言の楽しみの1つです」
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 櫛引庁舎 総務企画課
〒997-0346 山形県鶴岡市上山添字文栄100番地
電話:0235-57-2111
FAX:0235-57-2117