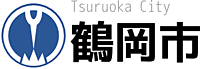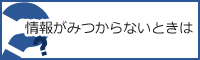【終了しました】平成28年度 晩秋蚕飼育について~新文化会館本緞帳「繭人」プロジェクト~
更新日:2017年1月12日
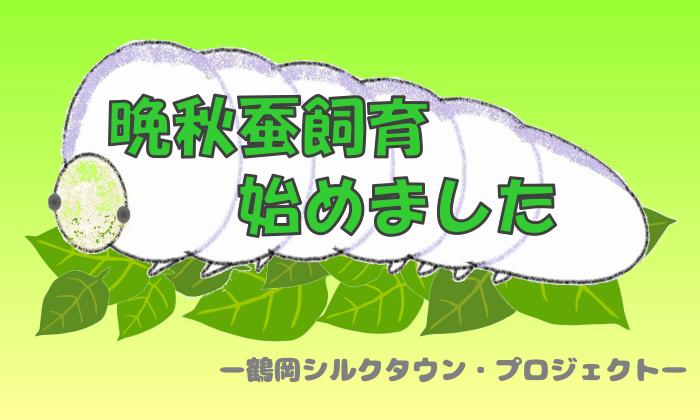
晩秋蚕飼育はじめました
≪概 要≫
晩秋蚕とは、秋に掃き立て(孵化)した蚕のことです。今回鶴岡市で飼育する錦秋鐘和(きんしゅうしょうわ)は、8月24日に掃き立てし、約4週間で繭になります。
「鶴岡シルクタウン・プロジェクト」では、絹文化、養蚕に関する啓発事業として主に春蚕飼育(6月)の時期に蚕飼育キットの無料提供を行い、幼稚園や保育園、小学校、福祉施設、個人の繭人などに飼育体験に取り組んでいただいておりますが、このたび、現在改築中の文化会館に設置される本緞帳(ほんどんちょう)の素材の一部に「鶴岡シルク」が活用されることから、本プロジェクトの一環として晩秋蚕飼育の「繭人(まゆびと)」を募集し、市民の皆様より生糸生産にご協力いただいております。
今年は9月1日に「おカイコさまの蔵」(松ヶ岡開墾場地内)にて配蚕し、9月下旬に繭になるまで各繭人が飼育を行います。また、松ヶ岡開墾場では三番蚕室にて約6000頭の飼育を行っています。
【飼育体験お問合せ先】
おカイコさまの蔵(松ヶ岡開墾場地内)
TEL 0235-64-1331
鶴岡シルクタウン・プロジェクト事務局(市役所政策企画課)
TEL 0235-25-2111(内線525・526)
≪晩秋蚕飼育実施状況(H28.9.1現在)≫
定員を上回るお申込みをいただきありがとうございました!ベテランの繭人から初めての方も含めて、幼児から大人まで多世代の方にご協力いただいています。
| 区分 | 件数 | キット数 | 頭数 |
|---|---|---|---|
| 保育園・幼稚園 | 6 | 9 | 270 |
| 高校 | 1 | 5 | 150 |
| 企業・施設等 | 2 | 2 | 60 |
| 個人 | 31 | 40 | 1200 |
| 小計 | 40 | 56 | 1680 |
| 市役所 | - | - | 90 |
| おカイコさまの蔵(松ヶ岡) | - | - | 5730 |
| 合計 | 40 | 56 | 7500 |
※1キット=30頭
≪晩秋蚕飼育日記≫
市役所では、総務課秘書係(3階)・政策企画課(5階)の他、櫛引庁舎にある社会教育課(2階)のカウンターで飼育しています。その様子を随時このページで報告していきますので、市役所にお立寄りの際はぜひ蚕に会いに来てください♪
【9月1日(木曜日) 晴れ】 3齢2日目
約1.8cmのお蚕様たちが市役所に到着しました。3齢はまだ小さいので、桑も小さく切ってあげます。今日「おカイコさまの蔵」に取りに来ていただいた繭人の方たちも、「おぉ~!」「ちっちゃ-い!」と言いながら引き取っていかれました♪
繭になるまで約3週間、大事に大事に育てていきましょう。
<桑の保管方法>
数日分の桑をまとめて保管する場合は、枝から葉を外し、濡らした新聞紙に包んでから冷蔵庫に入れておくと長持ちします。冷蔵庫がない場合は保冷剤と一緒にやクーラーボックスで保管してください。
霧吹きなどがあると楽です
ビニールに包むとさらに乾燥が防げます
【9月2日(金曜日) 晴れ】 3齢3日目
約2.2~2.3cmほどになったお蚕さまたちは気温も高くて元気に過ごしています。まだ1回にあげる桑の葉は5~6枚で間に合うので給桑も楽です♪
明日は飼育表によると「3眠」の予定ですが、今食べているペースを見てると明日は3齢4日目になるかもしれません。繭人の皆さんもお蚕さまが頭を上げて動かなくなっている状態を確認してから桑をやめてくださいね☆
3齢は桑を小さく切ってからあげるので、その分パリパリと乾燥してしまうのが早くなってしまいます。桑が枯れてしまうとお蚕さまたちは食べないので、長持ちさせるために、桑の乾燥が気になる時は濡らした新聞紙をかぶせておきます。

これは櫛引庁舎2階にある社会教育課のカウンターで飼育しているお蚕さまたちです。お蚕さまは気温などで成長に差も出るので、この飼育日記ではこちらの様子もたまにアップしていきたいと思います♪
【9月3日(土曜日) 晴れ】 3齢4日目
予想どおり3齢が延び、4日目に入りました。約2.5cmになったお蚕さまたちは、夕方には「眠」になった子も確認できたので、明日は”3眠”になると思います。明日の朝の状態を見てからにはなりますが、繭人の休息ということで明日は桑をあげるのをやめる予定です。「おカイコさまの蔵」や社会教育課のお蚕さまたちも、チラホラ”眠”の子が出てきているようです♪
※「眠(みん)」とは…
脱皮前の段階で、桑を食べなくなり足場を固定して動かなくなる状態のことを言います。
丸で囲んであるのが頭を上にあげて動かない「眠」の状態です

社会教育課のお蚕さまたちも同じペースのようです
【9月4日(日曜日) 晴れ】 3眠
朝には7割ほどのお蚕さまが”眠”となっていたので、今日1日は桑はあげないことにします。”眠”の日は脱皮の邪魔をしないように、「触らない」・「動かさない」を守って見守ります。頭を上にあげてピタッと止まっている様子がかわいいです♪
足場を固定して脱皮の準備中です
定規の上で”眠”になっていました
【9月5日(月曜日) 晴れ】 4齢1日目
昨日のうちにほとんどのお蚕さまが脱皮を終えて、体は少し白くなり、体長は3cmを超えてきました。脱皮後の殻を写真に撮り忘れてしまいましたが、社会教育課の写真(4枚目)にはチラホラ写っていますね♪気温が暖かく安定しているおかげか、市内の「繭人」が飼育しているお蚕さまたちも同じくらいのペースで成長しているようです。
桑をあげた瞬間ハイペースで食べています

社会教育課のお蚕さまたちも脱皮完了です
【9月6日(火曜日) 晴れ】 4齢2日目
今日も暖かく、お蚕さまたちは過ごしやすそうです。体長は約3.5cmと順調ですが、幅もぷっくり成長してきたので一気に大きくなった気がします♪桑の葉が少し固めだったので、お蚕さまたちが食べやすいように切ってあげてみました。角が多い方がお蚕さまは食べやすいそうです。
【9月7日(水曜日) 晴れ】 4齢3日目
大きい子は約4.5cmにもなっていて、昨日から1cm近くも大きくなっているかと思うとびっくりです!!政策企画課で飼育しているお蚕さまたちは頭でっかちに成長していますが、農政課のお蚕さまたちはまだ一回り小さかったり、「おカイコさまの蔵」のお蚕さまたちは小顔だけど長く成長していたりなど、飼育環境によってバラつきが出てきているようで、改めて生き物の不思議・育てるおもしろさを感じています♪
【9月8日(木曜日) 晴れのち雨】 4齢4日目
今日は桑を食べるペースが少しゆっくりになったように見えました。冷房の影響でお蚕さまたちにとってはちょっぴり冷えすぎなのかもしれません。桑の減りも少なく休憩時間が長いお蚕さまたちを見てると"繭人"としては心配になります。今週末に無事"4眠"になってくれるといいな-。
【9月9日(金曜日) 晴れ時々雨】 4眠
"3眠"が1日遅れだったので気を抜いていましたが、今日"4眠"に入りました!!昨日桑を食べなくなった様子に心配していましたが、"眠"の前兆だったようです。明日5齢に入ったらひたすらモリモリ食べるので、今日のうちに繭人は休憩しておきます♪
こんなに反って疲れないのかな?

社会教育課のお蚕さまも"眠"に入ってきました
【9月10日(土曜日) 雨のちくもり】 5齢1日目
脱皮を終え、体長も5cmを超えてきたお蚕さまたちは食欲も増してきたようです。これからは繭になるまでどんどん食べ続けます。特に成長が遅れている子も見られないので、このまま病気にならずに大きくなってくれることを願ってます♪
すっぽりと脱ぎ捨てられた殻が残されてます
【9月11日(日曜日) 晴れ】 5齢2日目
5齢に入ると食欲に比例して成長のスピードも早く、昨日から1cm以上大きくなっている子もチラホラいました。お蚕さまが桑の葉を食べる音のことを「蚕時雨(こしぐれ)」というそうですが、確かにこのぐらい大きくなると雨音のような大合唱が聞こえるのです。素敵なネーミングですよね♪いつもひたすらシャクシャクと桑を食べるお蚕さまの姿に癒されているのですが、5齢ではこの「蚕時雨」の音にも癒されています。

社会教育課のお蚕さまも脱皮を終えたようです
【9月12日(月曜日) 晴れのち雨】 5齢3日目
お蚕さまたちを手で持ってみると体の弾力が増してずっしり感が出てきました。白くてスベスベしているので思わず撫でてしまいます♪きっとお蚕さまたちはほっといてほしいんだろうなと思いながらも可愛くて我慢できないんです…。
【9月13日(火曜日) 晴れ】 5齢4日目
約7.5cmになったお蚕さまたちは相変わらずモリモリ食べていて、体はますますプリプリになってきました。お蚕さまを見ていた方が、「赤ちゃんみたい♪」と可愛がっていましたが、"食べて出して休んで(寝て)"のサイクルは確かに赤ちゃんみたいですよね♪

5齢に入るとお蚕さまたちが食べた後の桑の葉はたまにこんな感じになっています。
葉脈だけを残してきれいに食べてくれるので、その食欲にびっくりしてしまいます。
<蔟(まぶし)の作り方>
5齢に入ったら、上蔟(じょうぞく)に向けて蔟を用意しておきます。簡単にできるので、初めて飼育する繭人の皆さんも参考してみてください♪
※「蔟(まぶし)」とは…お蚕様が繭(まゆ)を作る部屋のことです。
※上蔟(じょうぞく)とは…繭を作る部屋(=蔟)に上ることです。
材料は厚紙のみです。お家だったらお菓子の空き箱などでも大丈夫です。
今回は横7マス×縦5マスの全35マスの蔟を作ります。
厚紙を4cm幅に切ります。今回は7×5なので、合計14本切りました。
横のものは4cm幅に、縦のものは5cm幅に印を付け、約2cmの切込みを入れます。
切込みを等間隔に入れることで、できた時の歪みが少なくなります。
切込みがある側を組み合わせていきます。厚紙が厚いと組み合わせるのが大変ですが、強く引っ張ると切込みのところから千切れてしまうこともあるので、丁寧に組み合わせてください。
これが完成品です。このように1つの蔟でもいいですし、マスが少ないものをいくつか作ってもかまいません。
ただし、お蚕さまが上から落ちてしまうことも考え、縦に段数が多いものはお勧めしません。
【9月14日(水曜日) 晴れ】 5齢5日目
本当にどんどん桑を食べるのでこちらもどんどん桑を用意していますが、数日に1回のペースで桑を取りに行くので、保管する冷蔵庫は桑の葉でパンパンになってしまいます。あと数日で繭を張り始めてしまうので、今のうちによく観察しておきます♪
【9月15日(木曜日) 晴れ】 5齢6日目
日中はまだ暖かい日が続いているので、お蚕さまたちにとってはちょうどいい環境ですね。政策企画課のカウンターで飼育しているお蚕さまは今日1頭お亡くなりになってしまいました。4齢になりたての時に怪しいなと感じていた子だと思うのですが、それからは順調に8cm近くまで大きくなっていたので、残念な結果になってしまってやっぱり寂しいです。晩秋蚕は春蚕に比べて桑の質や気温等の環境から飼育が容易ではないと言われていますが、お蚕さまたちに"命"を育てることの難しさも学ばせていただいているんだなと改めて思います。
【9月16日(金曜日) 晴れ】 5齢7日目
約9cmになったお蚕さまたちは飼育ケースを埋め尽くすくらいプリップリのパンパンに成長して、見る人見る人が「おっきい-!」とびっくりしながら見ていきます♪予定どおりいけば明後日には上蔟(じょうぞく)になるので、最後まで気を抜かずにお世話したいと思います。

社会教育課の蔟(まぶし)も完成したようです
「おカイコさまの蔵」のお蚕さまも大きく成長していました
【9月17日(土曜日) 晴れのち雨】 5齢8日目
追い込みのようにムシャムシャ食べているお蚕さまたちはまだ色が白いので今日は繭を張りそうにはありません。今日から天気が悪い日が続きそうなので、寒くなる前に繭になってくれるといいな-と思います。初日の写真と比べると約3週間でこんなに大きく成長するものだと感動します♪
【9月18日(日曜日) 晴れ】 5齢9日目
朝はまだ体も白いままで桑の葉も食べていましたが、午後になると熟蚕(じゅくさん)のお蚕さまがチラホラ出てきました。明日はいよいよ上蔟になりそうなので、変なところに繭を作ってしまったり2頭が同じ部屋に入らないようにこまめに見てあげようと思います。他の繭人さんのお蚕さまはすでに繭になっているところもあるそうです♪
※熟蚕(じゅくさん)とは…
体は縮み、黄色っぽい透き通るような色になり、桑も食べなくなり糸を出し始める状態のことを言います。
この写真でいうと、下側のお蚕さまが黄色がかっていて熟蚕の状態です。お蚕さまは繭を作るときに上に登る習性がありますが、熟蚕の状態になったら蔟(まぶし)に移してあげるとちゃんとお部屋で張ってくれる確率が高くなります。
【9月19日(月曜日) 雨のちくもり】 上蔟1日目
1日の間に約3分の2のお蚕さまが蔟の個室に入り繭を作り始めました。繭を作る前の最初で最後の排尿のタイミングが難しく、他の繭にかからないように上の部屋から入室させたかったのですが、お蚕さまたちはそんなこと関係ないのでウロウロした後は下の部屋にもどんどん入ってしまいます♪まだ熟蚕になっていない子もいるのですが、今晩ほとんどの子が上蔟になると思うので、繭人としては寝ずに見張るか悩んでしまいます…。
【9月20日(火曜日) 雨のちくもり】 上蔟2日目
政策企画課のお蚕さまたちは1頭を残してすべて繭を作り始めました。残りの1頭も熟蚕にはなったので明日には繭を張るでしょう。光にかざすと繭の中のお蚕さまが糸を吐いている様子が透けて見えて観察が楽しいです♪
秘書係で飼育しているお蚕さまたちも続々と上蔟していましたし、「おカイコさまの蔵」の約6,000頭も今日上蔟予定とのことです♪
秘書係の蔟(まぶし)は2棟建設したようです♪
【9月21日(水曜日) 晴れ】 上蔟3日目
とうとうすべてのお蚕さまが繭を作りました!!繭を作っている途中で力尽きてしまったのか病気にかかっていたのか、1頭が亡くなってしまいました。お蚕さまが亡くなる原因は色々あるようですので、繭人としてもう少し勉強しないとだめだな-と反省です。
汚れがほとんどないきれいな繭ができそうです♪

社会教育課のお蚕さまは半分ぐらい上蔟しました♪
【9月22日(木曜日) くもりのち雨】 上蔟4日目
この段階になるとお蚕さまの姿も確認できないので飼育日記の写真も変わり映えしないものになってしまいます♪最初に繭を作り始めたお蚕さまたちは、おそらく昨日あたりで約1.5kmとも言われる糸を吐き終え、蛹(さなぎ)になる前の"眠"の状態になっていると思います。これから脱皮をし、約7日で蛹になっていくそうです。
【9月28日(水曜日) くもりのち雨】 蛹化完了
繭を1つ振ってみると「カサカサ」という音がして、繭の中でちゃんと蛹になってくれたようです。今回の晩秋蚕飼育でできた繭は文化会館の本緞帳制作のための生糸にする予定なので、蚕蛾(カイコガ)として羽化はさせずに、すべての繭を蔟から外して約3日冷凍庫で保管します。
私たちが食事をする際に言う「いただきます」は、生産者等関わったすべての人や「命をいただく」ことへの感謝の言葉であり、食べることのありがたみを実感することでもありますが、こうして約1ヶ月の飼育体験をしてみると、「お蚕さまの命をいただく」ことへの感謝と、物のありがたみというものを改めて感じられるように思います。
白い繭ができました
【10月11日(火曜日) 晴れ】 集繭
今回飼育体験にご協力いただいた「繭人」の皆様から続々と繭が届いています!飼育の様子を伺うと、やはり春蚕(6月)に比べて飼育が難しいようで、途中で弱ってしまうお蚕さまもいたようです。
ご回答いただいたアンケートでは、「桑の葉を取ってくるのが大変だった」、「繭にならずに亡くなってしまう子がいた」など生き物を育てる難しさを感じた方が多い一方で、「蚕を育てるのが楽しかった」、「愛情が大きくなりすぎて冷凍庫に入れるのが辛かった」、「文化会館の完成が楽しみになった」、「また飼育体験をしてみたい」などの前向きなご意見をたくさんいただけました。アンケートの回答欄に収まらず、裏面の余白にびっしり感想を書いていただいた方や、温かいお手紙まで書いていただいた方など、本当にありがとうございました!
また、この飼育日記をチェックしていただいていた方もいたようで、要望欄にいただきました共感や応援のメッセージもとても嬉しく思っています。その中に、「お蚕さまロスはどうしたらいいか?」のご質問がありました。毎年「繭人」として飼育していく中で、生糸として使用するためとはいえ冷凍庫に入れることをためらうこともありました。今回は文化会館の本緞帳制作が目的でしたので繭の状態でご提供いただくこととしておりましたが、次回飼育をする機会がございましたら、成虫への羽化まで観察してみると理解が深められるかもしれません。
「繭人」の皆様が大事に育ててご提供いただいた繭については、本緞帳ができるまでの過程を追いながら、随時共有させていただきたいと考えています。この飼育日記については本日で一旦終了させていただきますが、「繭人」の皆様にはまた別途お知らせいたしますので、今後も「繭人」として鶴岡の絹文化にご興味を持っていただけたら幸いです。
これまでご覧いただきありがとうございました!
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Readerのダウンロードページへ
Adobe Readerのダウンロードページへ
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 政策企画課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1184
FAX:0235-24-9071