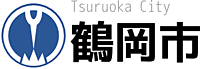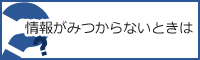第8回 石塚寛一さん(株式会社治五左衛門)
更新日:2025年1月30日
代々続く農家"治五左衛門"(じござえもん)の15代目である石塚寛一(いしづかひろかず)さん。農業に携わる中で、伝統的な技術を継承しつつ、新しい挑戦を積極的に行い、地域農業の発展に貢献しています。そんな石塚さんに、農業に対する想いや、今後の展望をお伺いしました。
はじめに、“治五左衛門”農園についてご紹介ください。
「治五左衛門」という名称は、石塚家に代々受け継がれてきた屋号です。3年前に法人化した際、この伝統ある名前を法人名としても引き継ぎました。治五左衛門の歴史は1644年、江戸時代の初期、徳川家光の時代から始まっています。
私が農業を始めた当初は、先代と同様にお米を主力として栽培していました。その他、ハウスメロンやカブなども手掛けており、特に最初に取り組んだメロン栽培では、糖分の
現在では、売上の約7割がだだちゃ豆です。そのほかにも、ミニトマト、赤カブ、ふきのとう、もち米などを生産しており、それぞれの特性を活かした栽培に取り組んでいます。
※転流:光合成によって作られた栄養分が、果実等に移動すること。

山形セレクションに認定された「だだちゃ豆」

藩主にも献上されていた「寺田餅」
収穫された赤カブ
収穫されたふきのとう
子供の頃から農業を継ぐことは意識されていたのでしょうか?
小さい頃から自然と「いずれ農業をするのだろう」と思っていました。田んぼで稲刈りを手伝いながらお菓子を食べたり、畑にいる時間が心地よかったのを覚えています。しかし、すぐに農業を始めるのではなく、大学卒業後は食品の輸出入商社に勤めました。農産物の流通や加工に携わることで、農業に役立つ知識を深めたかったからです。
だだちゃ豆へのこだわりや取り組み、その背景を教えてください。
ある年、お客様から「美味しくない」とご意見をいただいたことがあります。それは、ある品種が終盤を迎え、次の品種が始まるまでの、端境期(はざかいき)に収穫された豆だったからでした。これを機に、常に旬の美味しいだだちゃ豆を提供するため、香りや甘みの強いものを固定化させる努力を続けてきました。一つの品種を安定化するには5~7年の時間がかかります。現在では20種類を作付けしており、端境期なく常に美味しいだだちゃ豆を提供できるようになりました。
これからの農業における目標や展望を教えてください。
気候変動など厳しい状況が続く中でも、品質の高いだだちゃ豆を安定して提供できるよう、さらに努力していきます。そして、加工品の展開や、庄内の農業をより広く知っていただけるような活動を続けたいと思っています。いつか、だだちゃ豆畑を活用したビアガーデンを開催するなど、畑という特別な空間で、この地を訪れた人たちと地域の人たちが、収穫したばかりの新鮮なだだちゃ豆を味わいながら、地元のビールやワイン、日本酒を楽しめるような、そんな企画をやってみたいですね。
吉村美栄子知事より「ベストアグリ賞」の受賞を受ける石塚さん
.
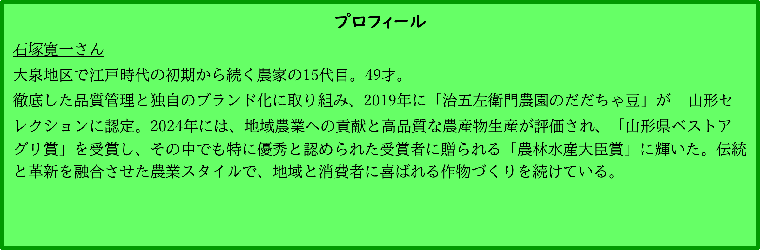
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 農政課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1295
FAX:0235-25-8763