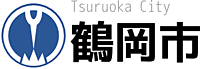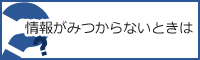【まち活掲示板】地域のまちづくり活動についてお知らせします
更新日:2025年9月25日
鶴岡市には、町内会や自治会など463の単位自治組織と、33の広域コミュニティ組織(コミュニティ振興会、自治振興会等)があり、地域のまちづくりの活動主体として取り組んでいます。
近年、多くの地域コミュニティでは、役員の高齢化や固定化、価値観の多様化や帰属意識の低下など社会状況の変化に伴い、活動の担い手不足が一層深刻さを増す傾向にあります。一方、地域の将来像や活動計画を描いた「地域ビジョン」づくりを通して、住民同士が地域の将来のことを話し合い、地域の特性や事情を踏まえた住民主体による地域づくりで成果をあげている地域も現れています。
目 次
1. 活動レポートを紹介します ~「まち活通信」から~
- まちづくり活動をお知らせする広報紙「まち活通信」では、地域のコミュニティ活動の工夫や独自の取組みなどを紹介しています。「まち活通信」から4事例を紹介します。
「まち活通信」はこちらからも閲覧できます。
![]() vol5 2025(令和 7)年 10月(PDF:1,679KB)
vol5 2025(令和 7)年 10月(PDF:1,679KB)
![]() vol4 2025 (令和 7)年 1月(PDF:1,582KB)
vol4 2025 (令和 7)年 1月(PDF:1,582KB)
![]() vol3 2024 (令和 6)年 9月(PDF:2,094KB)
vol3 2024 (令和 6)年 9月(PDF:2,094KB)
![]() vol2 2024 (令和 6)年 3月(PDF:1,625KB)
vol2 2024 (令和 6)年 3月(PDF:1,625KB)
![]() vol1 2023 (令和 5)年 3月(PDF:1,671KB)
vol1 2023 (令和 5)年 3月(PDF:1,671KB)
ご近所同士の支え合い体制の確立に向けて
城北町内会 会長 飯野 勝巳 さん
城北町は、今年、町内会発足から50年という節目を迎え、「心を豊かに助け合い、楽しく明るく、ふれあいの町づくりをめざして」というスローガンのもと、活動を続けています。
しかし、少子高齢化が進み、高齢夫婦世帯や単身高齢世帯が増加しています。これに伴い、地域福祉や自主防災活動の重要性が高まってきました。
「おたすけ会員」「おねがい会員」制度の導入
令和3年、山形県沖地震などの災害を踏まえ、防災意識を高めるため、町内会防災マニュアルの見直しを始めました。大規模災害が発生した場合、個人や家族だけで対応するのは難しく、隣近所との協力が不可欠だと考えたためです。そこで、災害時の要支援者と支援協力者の把握のため、「おたすけ会員」「おねがい会員」の登録制度を導入することとしました。「おねがい会員」は避難時に支援を希望する高齢者や障害者、「おたすけ会員」は「おねがい会員」を支援する人です。
活動開始当初、「おねがい会員」は38名でしたが現在は61名に、「おたすけ会員」は72名から135名に増えました。「おたすけ会員」の中には、女性の方や夫婦で登録してくださった方、さらには夜間や休日など限られた時間の中で協力してくださる方もいます。住民の高齢化に伴い「おねがい会員」の増加は予想していましたが、「おたすけ会員」が増えたことには驚きと喜びがありました。少しずつではありますが、ご近所同士で支え合う体制が整ってきたと感じています。また、「おたすけ会員」の専用LINEグループに会員の60%が参加しています。これにより迅速かつ正確な情報共有が期待されます。
さらに、町内会で緑の旗を各家庭に配布し、旗を活用した避難訓練を実施しています。 避難訓練では、安全であることの合図として、旗を玄関に出してもらい、発災時には旗が出ていない家には役員や「おたすけ会員」が訪問して安否確認をします。これらの取組みは、要支援者の情報が十分に把握されていなかったことが被害の拡大につながった東日本大震災の教訓を踏まえたものです。
城北町では、高齢者や障害者などの要支援者が災害時に取り残されることがないよう、これからもご近所同士で支え合える体制の確立に向けて、さらに努力していきます。

避難訓練で使用する緑の旗
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
住み慣れた土地で安心して住み続けることができる地域を目指して
山五十川自治会 会長 三浦 市樹 さん
一つの集落で二つの古典芸能を保存継承
山五十川集落は、鶴岡市南西部(温海地域)の中山間に位置し、推定樹齢1500年の「山五十川の玉杉」(国指定天然記念物)をシンボルに、山形県指定無形民俗文化財の「山戸能」「山五十川歌舞伎」の二つの古典芸能を保存継承しています。
一つの集落で二つの古典芸能を保存継承している例は珍しいと言われていますが、若者から高齢者まで幅広い世代が関わり、「人づくりは地域づくり」として取り組んでいます。
近年は、生涯学習活動や小中学生の体験活動などを通じて地域内外の交流人口も増えていることなどから、「令和7年度山形県観光物産事業功労者表彰」の栄を浴することとなりました。
一方で、少子高齢化の時代をどう乗り越えていくか、厳しい現実に直面しています。二つの古典芸能をこれまでと同じように継承していくことは大変難しいことですが、地域の宝、地域民の誇りとして、工夫を重ねながら次の時代へと保存継承していきたいと考えていま
す。
支え合い「結の会」の発足
暮らしの面では、地域内のスーパーの撤退や診療所の閉所などが相次ぎ、特に車を持たない高齢者にとっては厳しい生活環境になりました。
また、高齢化率50%を超える当集落には一人暮らし高齢者が多く、以前から冬季間の玄関先の除雪やゴミ出し、夏場の庭の草刈りや庭木の剪定等の作業が大変だと言う声も多くあり、自治会内でも大きな課題として捉えていました。
これらの課題を克服しようと、自治会役員をはじめ地元有志が集い、令和4年5月に「山戸支え合い《結の会》準備会」を立ち上げ、以降13回の会議やワークショップ等を重ね、令和5年6月に支え合い「結の会」が誕生しました。
活動の基本は、有償ボランティアによる地域の支え合いで、利用者は事前に登録を行い、利用券を購入します。サポートを希望する際に申し込みを行い、活動会員のサポート終了後に利用した分の利用券を活動会員に渡すという流れになります。
設立から1年を経過した令和6年6月からは、「お出かけ支援」にも取り組み、通院や買い物の付き添い等のサポートも始めています。
支え合い「結の会」は、住み慣れた地域でいつまでも元気で暮らし続けたいという誰もが考える願いを、住民同士の支え合いにより一歩実現につなげています。その基盤となっているのが、「支える人」「支えられる人」の隔たりなく、お互いが感謝の気持ちを大切にし、生きがいややりがいを持つことです。これからも一つ一つの課題を乗り越え、暮らし続けられる地域づくりを目指して取り組んでいきたいと思っています。

通院や買い物の付き添 い等のサポートをする 「お出かけ支援」の様子
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
三瀬地区自治会 会長 加藤 勝 さん
三瀬地区は鶴岡地域の南部に位置し、西側が日本海に面し、三方を山に囲まれた地形です。地域内の平野部を3本の川が流れているため、「三瀬」という地名であると伝えられています。
三瀬地区の地域ビジョンづくり
平成29年度にまちづくり研修会を始動し、まちづくりの指針となる「キャッチフレーズ」づくりから地域ビジョン策定に取り組むこととなりました。地域の様々な団体が参加するワークショップを開催し、地域の現状把握を行い、令和2年3月に三瀬地区地域ビジョン「三瀬イズム 住むを楽しむコミュニティ」を策定しました。策定以降は、鶴岡地域まちづくり未来事業補助金を活用し、地域ビジョンで掲げた目標達成のための事業を実施してきました。
令和6年度は、「みんなで元気を生み出し発信するまち、みんなでつくる安心のまち、みんなで支え合うまち」をスローガンに、地域ビジョンのふり返りとアップデートを行いました。
酒田市日向地区から避難所運営を学ぶ
令和7年3月29日に、研修会「コミュニティ×防災(令和6年7月の豪雨災害対応の活動の中で)」を開催し、避難所運営への理解を深めました。
研修会前半では、酒田市日向コミュニティ振興会の工藤事務局長から地区の成り立ちや避難者受入れに至るまでの具体的な事例について説明いただきました。また、連携してカフェを開設した株式会社良品計画との関係や地域ビジョン策定の経緯などについても紹介があり、「いろんな世代がみんなで支え合える地域」というゆるやかなつながりを大切にした地域ビジョンがあったからこそ、豪雨災害時における避難者対応の受入れが可能になったのではないかと感じました。さらに、防災無線の音が全く聞こえなかったこと、避難者の話を何度も聞く必要があったことなど避難所運営における課題も共有されました。実際に災害が起きた時は避難所運営経験者がおらず、避難訓練どおりにはいかなかったという言葉が印象に残りました。
住民アンケートから避難のあり方を考える
研修会の後半では、鳥取大学地域学部の筒井教授と山形大学地域教育文化学部の熊谷講師を交えたクロストークが行われました。能登沖地震後に三瀬地区で実施したアンケートでは、津波想定浸水域がある三瀬第3地区、三瀬第4地区で8割を超える世帯で避難行動が取られたことや、滞在可能な避難先として豊浦中学校が最も多かったことなど地域の特徴について伺うことができました。
また、三瀬地区住民の不安、心配ごととして国道7号線が使えない時はどうするのか、近所の単身高齢者への対応はどうしたらよいか、ペットの避難はどうするか、といった課題が挙げられたことを知り、参加者で共有することができました。
災害に備えて
豪雨災害への対応と住民アンケートの解析を組み合わせた研修会により、我がごととして災害を考えることができました。特に高齢者の避難は、日向地区でも三瀬地区でも大きな課題です。
今年度配布した「三瀬地区防災の手引き」には、非常時の持ち出しリスト、地震発生時の対応などを掲載しています。災害の発生時にはお互いに思いやりの気持ちを持ち、生活の安全、安心を確保していけたらよいと思います。

避難所運営について説明をする 日向コミュニティ振興会の工藤局長(左)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
藤島地区自治振興会 会長 齋藤 昭彦 さん
住民の必要課題に取り組む自治振興会を目指す
平成26年、旧藤島公民館から藤島地区自治振興会に移行し、藤島地区地域活動センターを拠点に、幅広い分野の地域コミュニティを担うことになりました。そこで住民組織代表者によるワークショップを開催し、住民アンケートを実施しました。その結果をもとに地域ビジョン5か年計画を策定し、計画に基づいた活動に取り組んでいます。
さて、最近は少子高齢化などによる社会構造の変化だけでなく、諸物価の高騰、令和の米騒動と言われる過去に経験したことのないような、国民生活に直結する問題が突発的に起こっています。また、気象においても昨年7月に発生した三和地区を中心とした水害や、夏場の高温障害、夏日の著しい増加などが挙げられます。これらの現象は、少子化と相まって屋外での運動の制限や活動の縮小、運動会種目の減少、地域文化の継承や課題などに影を落としています。
安心・安全な地域づくり
防災に関する取組みの1つとして災害時には活動センターが指定避難所となり、職員が災害状況の把握や、各組織との情報共有にあたります。令和元年には携帯無線機が18町内会長と活動センターに配備され、災害時に運用しています。
また、地区一斉防災訓練を毎年実施しており、昨年11月の訓練では、911名の方が参加し、各家庭での初動訓練や、自主防災会で一時避難場所の開設・情報伝達・安否確認などを実施しました。情報伝達訓練では、各町内会で屋外防災無線による避難の呼びかけが行われ、住民が真剣な面持ちで参加していました。
さらに、指定避難所参集訓練では、避難者カードへの記入体験や、段ボールベッドの組み立て訓練、防災トイレの展示が行われました。
子育てしやすい地域づくり
住民アンケートで課題として挙げられていた小中学生の教育サポートにも取り組みました。今年も小学生の希望者を対象に、「夏休み宿題支援室」を開講し、おさらい帳などの宿題のサポートを行いました。学年ごとに地元の教員OBや大学生に指導をお願いし、わからない部分についてアドバイスをしていただきました。
また、年末年始休みには、「小学生書初め教室」も開催しています。基本的な筆の運びや書のポイントなどを学びながら、学年ごとの課題に取り組んでいます。
さらに、「中学3年生学習支援室」を来春の高校受験に向けて9月から毎週1回開催しています。この支援室では、英語又は数学を受講することができ、それぞれ教員OBから指導を受けて、受験対策の学習に取り組んでいます。
玄関先除雪で要配慮者を支援
住民相互の助け合いによる「玄関先除雪ボランティア活動」は、高齢者世帯及び要支援者世帯を対象に、町内会住民が1シーズンの除雪サポーターを担います。除雪依頼者はあらかじめ除雪券(500円/30分)を購入し、除雪要請は活動センターに連絡します。そして活動センターから除雪サポーターに除雪依頼をするシステムとなっています。
これらの事業のほか、当自治振興会では生涯学習・環境福祉・体育・防災防犯を中心に各種事業の企画・運営にあたっており、これからも住みよい地域づくりを目指して尽力していきたいと考えています。

小学生を対象とした 「夏休み支援教室」
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. 活動事例や課題を紹介します ~第2期地域コミュニティ推進計画に係る「ふり返りシート」調査報告書から~
市では、令和3年3月に「第2期地域コミュニティ推進計画」(計画期間は令和3年度~7年度)を策定し、地域コミュニティの維持・活性化に向けた取組みを進め、コミュニティ活動の充実を図っています。
計画では、目指す5年後の方向性と計画の柱のもと、地域ごとに町内会など単位自治組織の課題と、コミセンや活動センターの主な対象区域である広域コミュニティ組織の課題を取りまとめています。また、第2期計画では、住民自治組織からも毎年取組み状況を確認してもらい、その内容を市に報告していただけるよう、「ふり返りシート」の作成を依頼しています。
「ふり返りシート」調査報告書(概要版・詳細版)では、それぞれの住民自治組織から記入いただいた「ふり返りシート」から、なるほどな…と思う取組みや、真似できそうなもの、ヒントになりそうなものを抜粋して紹介しています。
![]() 住民自治組織によるコミュニティ活動の調査結果(R6概要版)
(PDF:552KB)
住民自治組織によるコミュニティ活動の調査結果(R6概要版)
(PDF:552KB)
![]() 住民自治組織によるコミュニティ活動の調査結果(R6詳細版)
(PDF:4,232KB)
住民自治組織によるコミュニティ活動の調査結果(R6詳細版)
(PDF:4,232KB)
![]() 「ふり返りシート」調査報告書(R5概要版)
(PDF:557KB)
「ふり返りシート」調査報告書(R5概要版)
(PDF:557KB)
![]() 「ふり返りシート」調査報告書(R5詳細版)
(PDF:4,229KB)
「ふり返りシート」調査報告書(R5詳細版)
(PDF:4,229KB)
![]() 「ふり返りシート」調査報告書(R4概要版)
(PDF:535KB)
「ふり返りシート」調査報告書(R4概要版)
(PDF:535KB)
![]() 「ふり返りシート」調査報告書(R4詳細版)
(PDF:3,916KB)
「ふり返りシート」調査報告書(R4詳細版)
(PDF:3,916KB)
![]() 「ふり返りシート」調査報告書(R3概要版)
(PDF:671KB)
「ふり返りシート」調査報告書(R3概要版)
(PDF:671KB)
![]() 「ふり返りシート」調査報告書(R3詳細版)
(PDF:3,848KB)
「ふり返りシート」調査報告書(R3詳細版)
(PDF:3,848KB)
3. 町内会に加入しましょう
町内会(自治会・住民会等)は同じ地域に住むものとして隣近所が助け合い、安全・安心で明るく住みよい地域を維持していく大切な組織です。ごみステーションの設置や清掃、防犯灯の管理及び広報の配布等は町内会等が主体となっています。
町内会(自治会・住民会等)への加入手続きなどについては、お住まいの町内会等にご連絡をお願いします。ご不明な点等ありましたらコミュニティ推進課又は各地域庁舎総務企画課へお問い合わせ下さい。
4. 地域コミュニティ活動における個人情報の取扱いについて
個人情報とは、名前や生年月日、住所、電話番号など、特定の個人を識別できる情報を指します。町内会など会員の名簿を作成している組織も、個人情報を取り扱う事業者として個人情報保護法のルールに従う必要があります。
町内会長さんを例に、個人情報の取扱いにおいて注意すべきポイントを4つ紹介します。
1つめ。個人情報を取り扱う場合、利用目的を特定してください。「この名簿は、町内会の運営や災害時の連絡で使用します。それ以外では使用しません」など、利用目的を特定することが重要です。もちろん、利用目的の範囲を超えて名簿を利用するのは、原則禁止です。
2つめ。利用目的は、個人情報を記入してもらう用紙や町内会規則などに記載し、本人にきちんと明示しましょう。
3つめ。名簿が保管されているパソコンは、セキュリティ対策ソフトをインストールし、名簿データにはパスワードを設定するなど、個人情報の漏えい防止を徹底してください。
4つめ。近くの商店街組合から、割引クーポンを配布したいので会員の名前を教えてほしいと言われた場合、教えることはできません。当初の利用目的の範囲外で取り扱う場合は、事前に本人の同意を得る必要があります。
ただし、例外として、法令に基づく警察からの照会や災害時の安否確認など、人の生命や財産を守る必要があり、本人の同意を得ることが困難な場合は、その限りではありません。
(政府広報オンラインより抜粋)
5. 各種様式
地域コミュニティ活動に関連した各種様式をダウンロードできます。
町内会関係(鶴岡地域)
総合交付金関係
【R6実績報告用】
【R7交付申請用】
公民館類似施設関係(鶴岡地域)
防犯灯補助金様式(更新・修繕)
![]() 【様式】防犯灯補助金申請書(Word)(ワード:41KB)
【様式】防犯灯補助金申請書(Word)(ワード:41KB)
![]() 【様式】防犯灯補助金申請書(PDF)(PDF:76KB)
【様式】防犯灯補助金申請書(PDF)(PDF:76KB)
![]() 【記入例】防犯灯補助金申請書(PDF)(PDF:129KB)
【記入例】防犯灯補助金申請書(PDF)(PDF:129KB)
![]() 請求書様式(Excel)(エクセル:48KB)
請求書様式(Excel)(エクセル:48KB)
![]() 請求書様式(PDF)(PDF:110KB)
請求書様式(PDF)(PDF:110KB)
![]() 【記入例】請求書様式(PDF)(PDF:351KB)
【記入例】請求書様式(PDF)(PDF:351KB)
↓補助金申請時の提出書類等はこちらから確認願います。
防犯灯や街路照明について(町内会等に対する防犯灯補助制度について)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Readerのダウンロードページへ
Adobe Readerのダウンロードページへ
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 コミュニティ推進課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1203
FAX:0235-25-2997