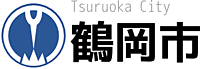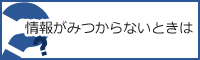広報つるおか2025.8月号
更新日:2025年7月28日
市長の一筆入魂(90)
こどもの頃の夏休み、田んぼの道からトンネルを越えて海へ。自転車で随分と遠くに出掛けた。自転車で行ける範囲も、小学校の低学年は集落内にとどまり、高学年になると学区内をあちこちと回れるようになった。中学生になると学区を越えて、あるとき、小波渡海水浴場に友人と2人で出掛けたことがあった。ちょっとした夏の冒険だった。
7月3日、栄地区のだだちゃ豆のほ場を訪問した。令和5年の猛暑、令和6年の大雨・日照不足の影響から、各農家は種子の確保に苦労していた。発芽率の低下が顕著となり、苗が確保できず、作付面積が減少した。種は農業の諸活動の根源と言える。一昨年の猛暑を受け、種子保存用の冷凍庫の導入を補助したが、更に将来を見据えた対応を検討する必要があると考えている。
水稲の転作作物である枝豆の作付面積の減少には、種の問題に加えて、米価の高騰による影響もあった。豆から米への作付けの転換が進んだのだ。そうした中、備蓄米の放出が進行し、米価が意図的に下げられることとなった。米政策には、生産面と消費面の両面からの対策が必要だ。政府が採った米価抑制策は、消費者への対策に偏り、生産者は得られるはずだった収入の機会を逃がすこととなった。一時的な米の増産の先に何が待っているのか、7月7日、国の担当者も出席し、鶴岡市農業振興協議会が開催されたが、その答えを見つけることは難しかった。
7月8日、鶴岡市水産振興協議会が開催された。令和6年度の県全体の漁獲額は、沖合のスルメイカの不漁などから18.1億円、前年比1.5億円減の過去最低となった。本市の漁獲額については11.2億円、前年比0.5億円の増となった。本市のスルメイカは沿岸操業のため、県全体の不漁よりも影響が小さかった。また、サワラの神経締めやズワイガニの冷やし込みなど、高鮮度・高品質を目指した本市の漁業者の取り組みが光った。
鶴岡市では、昨年度から市独自の「がんばる水産業応援補助金」に取り組んでいる。県と市の協調事業の補助金が不足する中、漁場環境の変化などに対応して設備を導入しようとする漁業者を応援する事業だ。中古船の購入や、冷水冷却装置、さらには、近年水揚げが増えているマグロ漁用の機器、GPS(全地球測位システム)の電波を受信し、自船の位置を海図上に表示する機器などの導入を支援している。6月24日に開催された山形県漁協の総代会において、私は、厳しい経営・漁場環境にある本県水産業の維持、底上げを図る観点から、本市の取り組みを紹介した上で、同じ庄内浜の酒田市、遊佐町でも頑張る漁業者を応援してほしい、と訴えた。
こどもの頃に歩いた砂浜、潜った海は、海洋環境の変化に直面している。7月11日、鶴岡市海岸保全に関する庁内ワーキングを立ち上げた。砂浜の減少に悩む由良地区などの声を踏まえ、課題を把握し、専門家につないでいきたい。
漁場・魚種の変化に加え、漁業者は、漁網や魚箱などの資材価格、燃料・電気代の高騰に向き合っている。市では、学校給食での地魚の活用を推進するとともに、10月には、「魚のおいしいまち鶴岡キャンペーン」を行うこととしている。今、私たちにできること、庄内浜の恵みを食べて応援することに、更なる協力をお願いしたい。
皆川 治
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 鶴岡市
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111
FAX:0235-24-9071