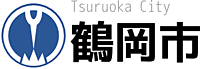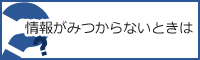広報つるおか2025.3月号
更新日:2025年2月21日
市長の一筆入魂(85)
1月21日、市長室にその電話はかかってきた。午前10時30分、約束どおりだ。受話器から「採択させていただきたい」という声が聞こえた。国の「地方大学・地域産業創生交付金」の採択が決まったのだ。
5年間で総事業費約22億円、その内国からの交付金約14億円の大型交付金だ。それまで採択された13件はいずれも県や政令指定都市、中核市の取り組みであり、本市のような規模の自治体が採択されたのは、今回が初めてだった。
「鶴岡ガストロノミックイノベーション計画」。その申請に向けて鶴岡市役所の企画部が動き出したのは昨年の5月だった。長い時間をかけて、粘り強くその取りまとめにあたったのは上野企画部長、齋藤政策企画課長の幹部職員とともに、若手職員コンビ、大滝さんとこども家庭庁から本市に出向し、政策企画課で働いている藤原さんだった。
山大農学部と慶應先端研などの関係機関と連携した若手職員の奮闘のおかげで、審査員が明かされないまま行われた現地評価など、厳正な審査をクリアすることができた。「いけるのでは」との期待は高かったが、電話の儀式が終わり、採択が決定、ほっと一息をついた。
2月3日、年初から新年会への出席と並行して続いていた新年度予算案の取りまとめ作業が終わった。一連の予算のヒアリング、査定を通じて改めて感じたのは、主体的に取り組むことの重要性だった。この事業は、何のためにやるのか。どんな意味があるのか。常に自問自答することで組織は強くなる。
国の水田政策、いわゆる5年水張ルールにも、何のために、どんな意味があるのか、という批判、反対の声が根強かった。水田活用の直接支払交付金という農林水産省の制度は、水田に着目した制度なので、水田であることの証明のために当該農地に5年に1回水を張ることを求めていた。本市の中山間地の代表的な作物であるそばなどでは、水はけを良くすることが必要であり、5年に1回水を張ることは、作付け・営農の断念につながりかねない。現場からは見直しを求める声が強く上がっていた。
2月4日に開催された鶴岡市農業振興協議会では、東北農政局の担当者から、令和9年度からの水田政策を抜本的に見直す検討が本格的に開始される旨の説明を受けた。令和7年度、8年度の対応としても、連作障害を回避する取り組みとして、土壌改良資材の散布などを行うことで、水張しなくとも交付対象となることが分かった。
「私は、常々、地方創生の本丸は、食・農業だと捉えてまいりました」と、現地評価の際に伝えた。採択された「鶴岡ガストロノミックイノベーション計画」は、山形大学、慶應義塾の国立、私立の枠を超えたカリキュラム再編を伴うものだ。
計画を実行し、食文化創造都市鶴岡に、新たな食・食関連産業を創出し、雇用を拡大していきたい。地方創生をリードしてきた基礎自治体として、地方創生の新たな展開の姿を示していく。
皆川 治
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 鶴岡市
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111
FAX:0235-24-9071